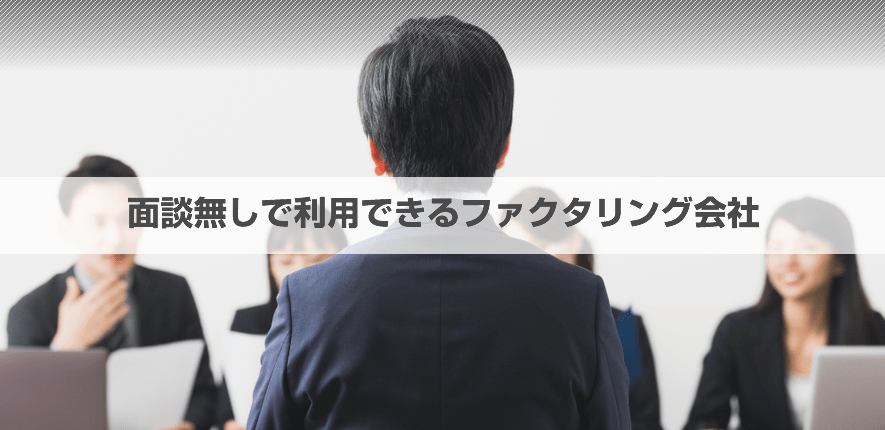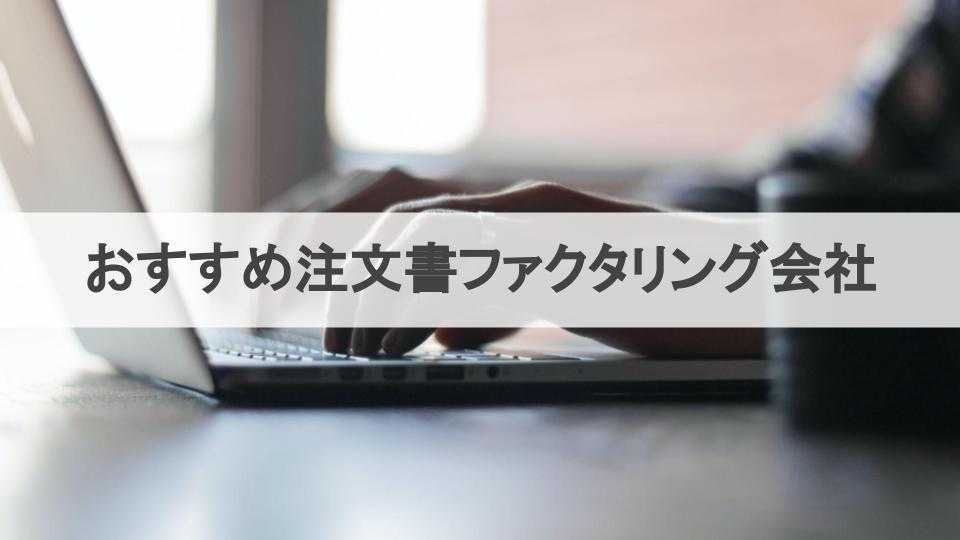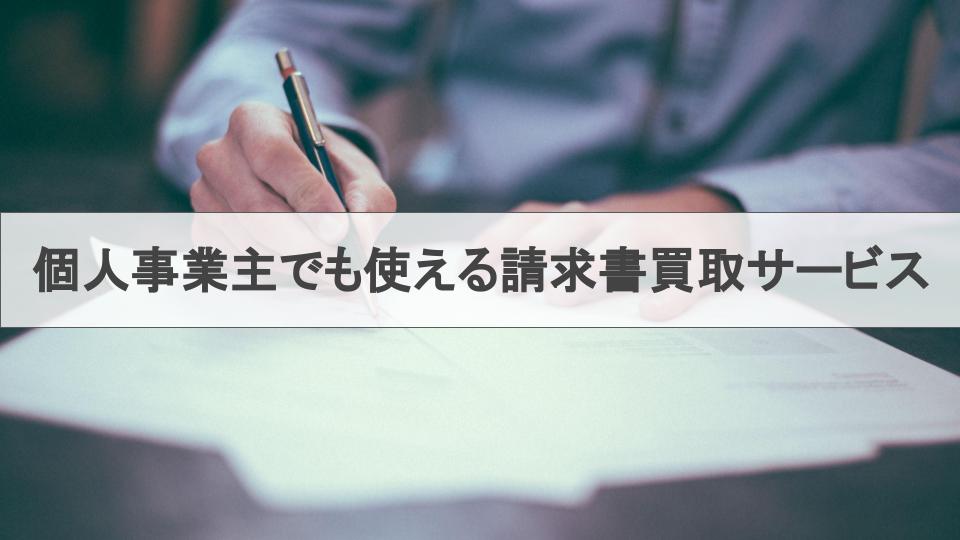「ファクタリングに種類があるって本当なの?」
「資金繰りには困っていないし、ファクタリングを利用する必要ないな」
「売掛先が海外企業だから、ファクタリングは利用できないよね?」
ファクタリング=資金繰り改善のためのサービス、と認識している方も多いのではないでしょうか。実際には、資金繰り改善が目的でないものや海外企業との取引で利用可能なものなど、種類があります。
本記事では、ファクタリングの種類を利用目的別にまとめています。さらに、取引の仕組みやメリットデメリットも併せて解説しているため、各種ファクタリングの基本情報を網羅的に把握することができるでしょう。
資金調達のためにファクタリングを利用する際は、自社の状況に最も適した種類を選んでください。
目次
ファクタリングとは
ファクタリングとは、自社の保有する売掛債権をファクタリング会社に譲渡し、資金を調達する金融サービスです。
企業間取引の多くは先に商品やサービスが提供され、支払いは後から行われます。入金までに期間があるため、通常の取引では急に資金が必要になった際に対応することができません。
緊急の資金調達に役立つのがファクタリングです。ファクタリングを利用すると、最短即日で、遅くとも本来の支払期日前には資金を調達することができます。
仕組みやメリットデメリットなどの基本情報は、次の章から説明していきます。
仕組み・支払いまでの流れ
ファクタリングは、売掛債権を売却し現金化する資金調達方法です。
基本的な仕組みは以下の通りです。
- ファクタリング会社に売掛債権の買取を申し込む
- 審査後、手数料を引いた額が入金される
- 売掛先から売掛金が支払われ次第、ファクタリング会社へ送金する
細かい点はファクタリングの種類により異なるため、利用するファクタリングの仕組みを確認しておきましょう。
メリット・デメリット
ファクタリングのメリットは以下の通りです。
- 素早い資金調達が可能
- 審査に通りやすい
一方で、以下のようなデメリットもあります。
- 手数料がかかる
- 違法業者が存在する
違法業者の存在については、本記事の最後で詳しく解説しています。
手数料相場
ファクタリングには手数料がかかります。一般的な手数料相場は1%〜20%です。ただし、ファクタリングの種類や会社、売掛債権額、売掛先の信頼性などにより手数料は変動します。そのため、実際に見積もりを出して確認することが重要です。
ファクタリングの種類
ファクタリングの種類は、大きく分けて「買取型ファクタリング」と「保証型ファクタリング」の2つあります。
買取型ファクタリングは、ファクタリング会社に売掛債権を売却することで現金を得るサービスです。基本的に、利用者は資金調達を目的としています。
買取型は最も主流なファクタリングサービスです。一般的にファクタリングというと買取型ファクタリングを指します。
保証型ファクタリングは、売掛金が支払われなかった際にファクタリング会社から保証金を受け取れるサービスです。主な利用目的は、貸し倒れリスクを回避することです。
買取型ファクタリング・保証型ファクタリングについて、次章で詳しく解説します。
買取型ファクタリング
買取型ファクタリングは、自社の保有する売掛債権をファクタリング会社に売却し、資金を調達する方法です。
現金化までの時間が早く、資金繰り改善が期待できるサービスです。一方で、利用には手数料がかかります。種類やファクタリング会社により異なりますが、基本的に設定される手数料は売掛金の1%〜20%です。
買取型ファクタリングは3種類に細分化されます。
- 買取ファクタリング
- 医療ファクタリング
- 将来債権ファクタリング
売掛債権を売却し資金を得る基本の仕組みは同様ですが、具体的な取引の仕組みや特徴は異なります。
買取ファクタリング
買取ファクタリングは、自社の保有する売掛債権を売却して資金を調達する方法です。取引形態により、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングに分けられます。
2社間ファクタリングは、ファクタリング会社と利用者(法人含む)の間で行われます。
仕組みは以下の通りです。
- ファクタリング会社に売掛債権を売却
- ファクタリング会社による代金の入金
- 売掛先から売掛金の支払い
- ファクタリング会社に売掛金を引き渡し
売掛金の未回収リスクに備え手数料は高く設定されていますが、売掛先が関与しないため手続きがスムーズに進行し、入金までに時間がかからないというメリットがあります。
ファクタリング会社、利用者に売掛先を加えて行われるのが3社間ファクタリングです。
2社間ファクタリングに比べ、取引が完了するまでの工程が増えます。
- 売掛先にファクタリング利用について通知・同意を取得
- ファクタリング会社に売掛債権を売却
- ファクタリング会社による代金の入金
- 支払期日に売掛先がファクタリング会社に支払い
以上が基本の仕組みです。
売掛先の同意が必要なため、資金調達までに時間がかかりますが、審査に通りやすく手数料も抑えられます。
買取ファクタリングには家賃収入を対象としたものもあります。
医療ファクタリング
医療ファクタリングは、医療機関や介護施設が得た各種報酬の債権をファクタリング会社に売却することで早期に資金を調達する方法です。診療・介護・調剤報酬債権ファクタリングと称されることもあります。
診療・介護・調剤報酬債権は、社会保険診療報酬支払基金(社保)や国民健康保険団体連合会(国保)など公的機関に請求し、入金が行われます。一般的に請求から入金まで2ヶ月ほどかかりますが、医療ファクタリングを利用すれば数日〜一週間程度で資金調達が可能です。
仕組みは、3社間の買取ファクタリングと大差ありません。
- 利用者(病院や調剤薬局、介護施設など)が各種報酬を社保・国保に請求
- ファクタリング会社が社保・国保に報酬債権買取を通知、了承を得る
- ファクタリング会社による報酬債権の買取・入金
- 社保・国保がファクタリング会社に報酬金を支払う
医療ファクタリングは、公的機関が債権の支払主です。ゆえに、ファクタリング会社からの信頼が厚く、審査に通りやすい、手数料が抑えられるなどのメリットがあります。
デメリットは、医療ファクタリングは高い専門知識を要するため、扱っているファクタリング会社が少ないことです。
診療報酬債権ファクタリング
診療報酬債権ファクタリングは国の機関である国民健康保険や健康保険組合と、医療機関、そしてファクタリング会社との3社間で行われます。
基本的なファクタリングの仕組みは一括ファクタリングと同じです。
- 医療機関とファクタリング会社が債権譲渡契約を結ぶ
- 医療機関は、ファクタリング会社を利用した旨を国保や協会けんぽに通知
- ファクタリング会社が医療機関に支払う
- 医療機関が国民健康保険団体連合会(国保連)に請求を行う
- 国民健康保険団体連合会(国保連)がファクタリング会社に支払う
ファクタリング会社は、買取額の7割から8割の金額を医療機関に支払うために診療報酬明細(レセプト)に不備がないか、架空請求はないかなどの審査をします。
国民健康保険団体連合会が債務者ですから、すべてのレセプト債が審査に通ると考えてよいですが、ごくまれに審査に通らない診療報酬明細もあるようです。
歯科診療報酬債権ファクタリング
歯科診療報酬債権のファクタリングも、基本は診療報酬債権のファクタリングと同じ流れです。
現在の歯科医院を取り巻く環境は悪化しています。
「コンビニより歯科医院のほうが多い」と言われており、経営破綻する歯科医院も増えています。
勤務医だった歯科医が独立開業するため都会では競争が激烈。
逆に地方では人口が減っており、思うように患者を獲得することができず歯科医院を畳むことも多いです。
また、歯科医院を開業する際には設備投資に資金がかかり、自己資金でまかなえる医師は問題ありませんが、ほとんどの歯科医は日本政策金融公庫などからの融資によって準備することも多いのです。
診療を始めてみたものの患者数は思うようには増えず、診療報酬の7割の入金は約2ヶ月後ですし、融資の返済もしなければなりません。
歯科診療報酬債権ファクタリングは、このタイムラグを早期に改善できる最善の策となるのです。
介護報酬債権ファクタリング
介護報酬債権のファクタリングも、診療報酬債権のファクタリングと流れは同じとなっています。
介護事業者の頭を悩ませる原因は、診療報酬の9割が約2ヶ月後に入金されますので、資金不足になってしまうことにあります。
また、福祉車両などの設備投資にもお金がかかります。
通常7割の診療報酬債権に比べると、介護診療報酬は9割という高い割合も事業者にとってネックとなっているのです。
介護事業をはじめて間もない事業者や多くの介護職員を雇用している事業者にとって、早期に介護報酬債権を現金化できるファクタリングは非常にニーズが高いといえるでしょう。
調剤報酬債権ファクタリング
調剤報酬債権のファクタリングも、診療報酬債権のファクタリングと流れは同じです。
薬剤料、医療材料費、薬剤技術料などがこの調剤報酬債権ファクタリングを利用できます。
薬局は、国の政策として院外処方箋を発行するように推し進められたことにより、病院のすぐ近くに数件の薬局が並ぶようになりました。
患者側から見れば、治療を受けて処方箋を受け取ったら、早く薬を受け取って帰宅したいと思うはずです。
薬局をなるべく病院の近くに隣接すれば患者を獲得できますが、そうでない場合は経営が厳しくなるでしょう。
調剤報酬債権も診療報酬債権と同じく、報酬の発生から入金まで2カ月近くかかります。
その間も人件費などの事業資金は必要になりますので、これらのタイムラグを解消するために調剤報酬債権ファクタリングは利用されています。
将来債権(注文書・発注書)ファクタリング
将来債権ファクタリングは、将来的に発生するであろう債権を売却することで資金を調達する方法です。例を挙げると、「毎月100万円を支払う」と特定企業と契約している場合、支払期日は未定でも債権の発生は推測できます。
将来債権ファクタリングの仕組みは以下の通りです。
- ファクタリング会社に将来債権買取の申し込み
- ファクタリング会社が将来債権の審査を行い、契約条件を設定
- 契約内容に同意した後、ファクタリング会社から入金
- 売掛先に商品やサービスの提供、請求書を発行
- 支払期日までに売掛先が入金
- ファクタリング会社に対して送金
将来債権は、数回に分けて少しずつ売却することで支払いの負担が減るというメリットがあります。
一方で、債権が未回収になるリスクが大きいために審査が厳しかったり、手数料が高かったりとデメリットもあります。
保証型ファクタリング
保証型ファクタリングは、売掛金が未回収になった際にファクタリング会社から保証金を得ることのできるサービスです。利用目的は貸し倒れの回避であり、資金の調達はできません。
保証型ファクタリングには以下の3種類があります。
- 保証ファクタリング
- 一括ファクタリング
- 国際ファクタリング
どれも資金調達ではなく、貸し倒れリスクに備えるために利用されます。
保証ファクタリング
保証ファクタリングは、売掛先が倒産するなど債権未回収になった際に、保証金を受け取れるサービスです。
仕組みは以下の通りです。
- ファクタリング会社に利用申し込み
- ファクタリング会社が売掛先の与信調査を実施
- 契約
- 支払いが行われなかった際に、保証金の入金
貸し倒れリスクに備えられることや、売掛先に保証ファクタリングを利用していることが通知されないというメリットがあります。
一方、利用には保証金が必要です。売掛金が無事支払われた場合でも、保証金は返ってきません。
メリット
保証ファクタリングを活用する最も重要なメリットは、取引先の金銭債権が保証されることによって、貸倒れの可能性を低減できるだけではありません。
販売先が倒産しても所有する金銭債権が保証されるだけでなく、支払企業の信用状況を随時確認できること、なにより新規の取引先であっても金銭債権の保証がなされることです。
以下では、それぞれについて詳しく確認していきましょう。
保証ファクタリングの一番のメリットはもちろん 貸倒のリスクから解放されることです。
それに付随して、保証ファクタリングを契約するときにファクタリング会社が取引先の与信審査を行ってくれるので、社内で与信審査をせずに済むというメリットがあります。
与信審査をファクタリング会社にアウトソーシングすることができるので、業務コストを大きく削減することができますし、なにより不安定な取引先とは今後信用取引をしないという決定もできて安心 です。
さらに、通常、新規の取引先については信用情報が全くない状態です。
しかし、ファクタリング会社は新規の取引先であってもどのような会社であるかを調査しているため、金銭債権の回収見込みを正確に判断することができます。
そのため、新規の取引先でも安心して取引を行えるようになります。
この3つが保証ファクタリングを活用する主なメリットと言えるでしょう。
デメリット
保証ファクタリングには上で説明したようなメリットがありますが、もちろんデメリットもあります。
保証ファクタリングについて、デメリットについても十分に理解しておかないと思わぬリスクを抱える可能性があるので注意が必要です。
まず、保証ファクタリングの手数料額です。
保証料は通常取引先の信用力によって変化し、信用力の高くない取引先の場合、その分だけ保証料も高くなります。
保証ファクタリングに2つ目のデメリットとして、保証サービスを利用する場合、取引先の信用力が著しく低下していると保証ファクタリングが利用できない場合があります。
ファクタリング会社がそれぞれ保証限度額を設定するために審査を行いますし、その審査はファクタリング会社独自の基準によって審査されることになります。
そのため、1年前は審査を通っていた取引先であっても、信用が著しく低下したような場合には、途中から保証を受けられなくなる可能性もあるので注意が必要です。
メリットもデメリットもある保証ファクタリングですが、どのような場合はサービスを利用する価値があるのでしょうか?
一括ファクタリング
一括ファクタリングは、売掛先・納入企業間の決済手続きを金融機関が一括で行うサービスです。従来の手形取引の代用法として利用されます。
一括ファクタリングは売掛先(支払企業)が利用を決めることが特徴です。他のファクタリングは納入企業が利用者でしたが、一括ファクタリングでは支払企業が利用者となります。
なお、近年の一括ファクタリングでは基本的に「でんさい(電子債権)」を扱います。多くの場合、納入企業・支払企業共にでんさいの導入が前提となるため注意してください。
取引の仕組みは以下の通りです。
- 支払企業が金融機関の一括ファクタリングシステムに登録
- 売掛金の発生
- 納入企業が金融機関に売掛債権を譲渡・支払企業が承諾
- 金融機関が納入企業に入金
- 支払企業が期日までに売掛金を金融機関に入金
買取型の3社間ファクタリングと仕組みは似ています。異なるのは、事前に支払企業が一括ファクタリングシステムに登録する必要があることです。
一括ファクタリングには以下のようなメリットがあります。
- 早期の資金調達が可能
- 貸し倒れリスクの回避
- 手形の印紙税の軽減
- 手形の紛失、盗難などのリスク回避
上2つは納入企業、下2つは支払企業のメリットです。
一方、デメリットも存在します。
- 審査が厳しい
- 支払企業の事前のシステム登録が必要
一括ファクタリングは、基本的に銀行が売掛債権の買取などを行います。ゆえに、審査は他のファクタリング以上の厳しさです。言い換えると、一括ファクタリングの審査に通る支払企業は、十分な信頼性があるとみなされ、結果的に取引先からの信用度を高められます。
一括ファクタリングはでんさいファクタリングへ移行
一括ファクタリングは非常に便利な決済システムですが、利用率は縮小傾向にあるといいます。
その代わりに、でんさいという新たな仕組みを利用したファクタリングが増加しているのです。
ここで言う、でんさいとは、でんさいネットという銀行間のネットワークのことです。
このネットワークを通して電子登録された債権について、金銭債権を保有している会社・その取引先・銀行の3社間でやり取りする決済形態が、近年急増しているのです。
つまるところ、従来の紙ベースで行われていた一括ファクタリングが電子化されたというイメージとなります。
このでんさい一括ファクタリングは、先にも説明したように支払企業がファクタリング会社に対して依頼するものであるため、たとえでんさいネットに登録していない納入企業の場合でもでんさいを受け取ることができることが特徴です。
でんさいを使った一括ファクタリングを活用すれば、でんさいを導入したしたときと同様の効果を得ることができるばかりではなく、一括ファクタリングの効果も得ることができ、まさに一石二鳥。
次世代的な特徴を持つでんさいファクタリングは、今後もその需要を伸ばしていくものと考えられます。
国際ファクタリング
国際ファクタリングは、国際取引において売掛金が未回収となった際に、保証が受けられるサービスです。
基本的に、国際ファクタリングは以下の4社間で行われます。
- 利用者(法人含む)
- 国内ファクタリング会社
- 売掛先(海外企業)
- 国外ファクタリング会社
場合によっては、海外のファクタリング会社を介入しないこともあります。
国際ファクタリングの仕組みは以下の通りです。
- 商品の輸出前に利用者がファクタリング利用を申し入れ・売掛先が承諾
- 国内ファクタリング会社に利用申し込み
- 国内ファクタリング会社が国外ファクタリング会社に、売掛先の信用調査依頼
- 売掛先の信用を確認・利用者にファクタリング利用の承諾を伝達
- 4社間でファクタリング契約の締結
- 商品を輸出
- 輸出証明書を国内ファクタリング会社に提出
- 売掛金が未回収の場合、ファクタリング会社が利用者に保証金の支払い
国際取引では、輸送中の事故などにより売掛金が回収できなくなる可能性が高いため、国際ファクタリングの利用によって未回収リスクに備えられるのが利点です。
一方、国際ファクタリングを提供している会社は少数のため、選択肢は多くありません。
そもそも輸出業が抱える問題点とは?
海外輸出業の場合、取引相手の信用情報が国内の取引と比べて入手しにくいため、相手の支払い能力を見極めることが難しく、貸し倒れリスクを正確に見積もることができないことが問題です。
この傾向は、十分に取引相手の信用リスクを調査できない中小企業・小規模事業者において顕著。
そのため、債権管理・回収に係るリスクをどのようにヘッジするかが重要な課題として認識されるようになりました。
その結果、国際的に取引をする場合は国内外のファクタリング会社を活用して、海外取引先との取引の安定性を必要性が生じたのです。
こうした背景のもとで解決策として主流になっていったのが、信用状。
以下で、そんな信用状の役割について詳しく説明していきましょう。
貿易信用状(L/C)の役割
貿易信用状とは英語でLetter of Creditと呼ばれ、日本では「L/C(エルシー)」と呼ばれることが多いです。
貿易信用状は、現地の銀行が輸入業者の口座を作成し、輸出業者に対して輸入代金を支払うことを確約する書類として役立てられています。
簡単に言えば、L/Cとは輸出者に対して対価を支払うことを、銀行が保証する書類です。
貿易取引においては、商品の売買契約はお互いに外国の会社との契約となることから、輸出者側は商品を送っても間違いなく代金が受け取れるかどうか等について不安を抱えています。
一方で輸入者側は、代金を前もって支払った場合に、商品が間違いなく送られてくるかどうかについて不安を抱えています。
そこで、輸出者・輸入者双方の不安を解消し、取引の円滑化を図ることを目的に役立てられているのが信用状であり、信用状があることによってスムーズな貿易取引が可能となるのです。
信用状は法的にその権力が認められているものであり、絶対的な効力を持つ書類。
そのため、国際貿易において信用状は必要不可欠だったのです。
しかし信用状を請求するのが煩雑であることと、手続きに時間がかかることから信用状を利用した取引が、近年ではあるものに置き換わりつつあります。
次項で詳しく見ていく事としましょう。
L/Cから国際ファクタリングへ
信用状はその不便さから、「国際ファクタリング」に置き換わってきています。
信用状を使った取引と国際ファクタリングを使った取引の大きな違いは、債権債務に関するコストの負担者が異なるということです。
信用状の場合、輸入者が銀行に信用状の発行を依頼することになるため信用状の発行コストは輸入者が負担しなければなりません。
一方、国際ファクタリングでは、輸出者がファクタリング会社に依頼することになるため、ファクタリング取引のコストは輸出者が負担することとなります。
わざわざ輸入する度に時間をかけて信用状の発行を頼むのは非常に面倒。
こうした不満が急増し、>国際ファクタリングを利用した取引が急増しているというわけですね。
リバースファクタリング
その他のファクタリングとして、リバースファクタリングがあります。買取型、保証型のどちらにも属しません。
リバースファクタリングは、売掛金の支払いをファクタリング会社が立て替えるサービスで、支払企業(債務者)が利用します。
具体的なリバースファクタリングの仕組みは以下の通りです。
- 売掛金が発生
- 支払企業がファクタリング会社に利用申し込み
- 審査を経て、ファクタリング契約締結
- ファクタリング会社が本来の支払期日までに納入企業(債権者)に売掛金を支払い
- ファクタリング契約の支払期日までに支払企業がファクタリング会社に売掛金を振り込み
支払期日が伸びること、支払先の信用を失わないことなど利点がある一方、手数料が高額で、扱っているファクタリング会社が少ないというデメリットも存在します。また、でんさい(電子債権)の導入も必須です。
パナソニックも利用
パナソニックも利用したリバースファクタリングはどのようなサービスなのでしょうか?
そもそもリバースファクタリングの言葉に入っているリバースは、反転という意味があります。
ファクタリングが債権を譲渡して資金調達する方法ですが、反対にリバースファクタリングは債務を譲渡して支払い期日を遅くします。
パナソニックの例でいえば、パナソニックの債務である買掛金をファクタリング会社に譲渡し、ファクタリング会社がパナソニックに代わって債権保有会社に支払いをします。
数か月後、パナソニックはファクタリング会社にファクタリングの手数料込みで支払うという仕組みです。
パナソニックの下請け企業は早期に債権の回収ができますし、パナソニックは支払いを遅らせることができるというメリットがあります。
両者どちらにもメリットがあるのがリバースファクタリングなのです。
リバースファクタリングのメリット
売掛先、債権保有会社、さらには銀行やファクタリング会社にとってもメリットの多いリバースファクタリング。
この章では、それぞれの立場からメリットについて解説していきます。
売掛先のメリット
売掛先がリバースファクタリングを利用する最大のメリットは、支払期日を伸ばせることです。
たとえば3ヶ月伸ばすと、手元には支払う予定だった3ヶ月分のキャッシュが生まれます。
そのキャッシュで銀行融資を一括返済するといったことも可能になります。
もちろん3ヶ月後には、手数料を含めてファクタリング会社に支払いをしなければなりませんが、銀行の金利を完済まで支払うことに比べれば、大した金額ではありません。
債権保有会社のメリット
債権保有会社にもリバースファクタリングのメリットは大きいといえます。
まず、早期の資金化が可能です。
加えてファクタリングの手数料などは売掛先が負担しますので、売掛債権が100%回収できるのです。
債権保有会社はキャッシュフローに余裕ができますので、今後の事業計画もゆとりができるのではないでしょうか。
また、未払いや取り立ての手間がなく、売掛金を確実に回収できることも大きなメリットです。
このようにリバースファクタリングは、売掛先、債権保有会社双方が恩恵を受けることができるのです。
銀行やファクタリング会社のメリット
リバースファクタリングは、銀行にとってもメリットがあります。
企業はリバースファクタリングを利用して支払いを数ヶ月遅らせ、手元に生まれたキャッシュで銀行融資を一括返済してくれます。
そしてリバースファクタリングにかかる支払いは数か月後。
銀行は融資を滞りなく返済してもらえる上に、さらに手数料を受け取れるというメリットがあります。
言うまでもなくファクタリング会社にもメリットはあります。
規模の大きな取り引きを永続的に利用してもらうことで、大きな手数料利益が見込めます。
リバースファクタリングは、売掛先にとっても債権保有会社にとっても互いにwin-winなサービスであることは間違いありません。
さらに銀行とファクタリング会社にとってもメリットがあるのですから、これからリバースファクタリングはもっとメジャーになるのではないでしょうか。
リバースファクタリングの注意点
リバースファクタリングは、パナソニックのような規模の大きな企業が利用するサービスであること、それがゆえに金額が莫大です。
「でんさいのメリットとデメリットとは?」でも紹介しているように、中小のファクタリング会社では今のところ取扱がありません。
唯一、リバースファクタリングに近いサービスを取り扱っているのが、みずほファクターのみずほ電子債権決済サービス(電ペイ)です。
みずほ電子債権決済サービス、通称「電ペイ」は、みずほ独自の電子債権決済サービスのため、他の電子記録債権サービスとの互換性がありません。
みずほ銀行と取り引き実績がある企業のみ利用可能となっています。
ファクタリングや種類に関してよくある質問
ファクタリングやファクタリングの種類に関して、よくある質問をまとめました。
- ファクタリングは違法ではないの?
- 違法業者は存在する?避けるための注意点は?
- ファクタリング7種のうち利用者が多いのは?
ここからは各疑問について詳しく解説していきます。
ファクタリングは違法ではないの?
ファクタリングは、法的根拠のある合法的な資金調達方法です。
民法第466条に債権の譲渡性に関する以下の記載があります。
「債権は譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りではない。」
ファクタリング会社と利用者(法人含む)の間で行われるのは民法第466条で認められている売掛債権の譲渡です。よって、ファクタリングは合法的なサービスであるといえます。
違法業者は存在する?避けるための注意点は?
ファクタリング会社の中には、ファクタリングと称して融資を行う違法業者が存在します。
ファクタリングが売掛債権を利用した対等な取引であるのに対し、融資は金銭の貸付です。融資は返済義務があるため、売掛金が未回収となった際にリスクを背負うのは利用者(法人含む)となります。一般的なファクタリングであれば、ファクタリング会社が未回収リスクを背負います。
違法業者に騙されないよう、利用するファクタリング会社を見極めることが重要です。
違法業者の特徴は以下の通りです。
- ファクタリング会社の事業所、固定電話、公式ホームページが存在しない
- 見積書、契約書を発行しない
- 契約内容に不明瞭な点がある
- 「審査なし」と強調している
これらに該当するファクタリング会社の利用は避けましょう。
ファクタリング7種のうち利用者が多いのは?
ファクタリングの中で最も利用者数が多いのは、買取ファクタリングです。
2020年に行われたインターネット調査によると、ファクタリング経験者のうち40.6%が買取ファクタリングを利用していました。内訳は、2社間ファクタリングが27.3%、3社間ファクタリングが13.3%です。
次いで保証ファクタリングが15.9%、一括ファクタリングが11.6%という結果でした。
参考:ファクタリング(売掛債権譲渡)利用者への総合調査/2020年版リサーチ調査
一般的には、買取ファクタリングが主流だと考えられます。ただし、その他のファクタリングも利用者がいないわけではありません。他人の動向は気にせず、自社の状況に最も適したファクタリングを選びましょう。
ファクタリングの種類 解説まとめ
ファクタリングは大きく2種類あります。
- 買取型ファクタリング:売掛債権を売却し早期の資金調達が可能
- 保証型ファクタリング:売掛金未回収の際に保証金を受け取れる
ここからさらに、各3種類ずつに分けられます。買取型ファクタリングは以下の3種類です。
- 買取ファクタリング:債権を売却し資金調達。2社間と3社間に分かれる。早期の資金調達がメリット。
- 医療ファクタリング:医療機関や介護施設が各種報酬を売却する。メリットは手数料の低さ。
- 将来債権ファクタリング:将来発生する見込みの債権を売却する。支払いの負担が減ることがメリット。
保証型ファクタリングには以下の3種類があります。
- 保証ファクタリング:債権未回収の際に保証金を受け取る。メリットはリスクの回避が可能であること。
- 一括ファクタリング:手形取引の代わりに行われる。メリットは手形のコストやリスクの削減。
- 国際ファクタリング:国際取引における債権未回収時に保証金を受け取る。高い未回収リスクに備えられることがメリット。
また、買取型・保証型のどちらにも属さない、リバースファクタリングも存在します。他のファクタリングとの違いは、支払企業(債務者)が利用主であることです。ファクタリング会社が売掛金の支払いを立て替えるサービスであり、支払期日を延長できるというメリットがあります。
本記事ではファクタリング7種の仕組みからメリットデメリットまでを全て解説しました。
会社により、ファクタリングの利用目的や経営状況はさまざまです。利用者が多いから、手数料が安いからと安易に選んではいけません。本記事を参考に、自社のニーズに最も合うファクタリングを利用してください。
最適なファクタリングを利用し、自社の持つ課題を解決しましょう。